「副業したいけど会社にバレたらどうしよう・・・」
「確定申告が必要らしいけど、正直よくわからない・・・」
こんな悩みはありませんか?
近年は物価上昇、老後不安などの要因から、副業により収入を増やしたいと考える会社員が増えています。
働き方改革の影響で副業を認める企業は増えていますが、禁止する企業もまだ多いのが現状です。
会社に知られず副業したい方にとって、大きな障壁は「会社バレ」と「税金の知識」です。
この記事では、副業が会社にバレる理由と回避法、知っておきたい税知識、バレずに始めやすい副業のジャンルについて解説していきます。
副業を始める前に知っておきたいポイントをおさえることで、安心して副業のスタートを切ることができます。
- 副業が会社にバレる理由
- バレないためにおさえるポイント
- 副業に関する最低限の税知識
- 会社員が始めやすいおすすめ副業ジャンル
※僕は、会社の副業禁止に縛られすぎず、個人として複数の収入源を持つことが、これからの時代において必要不可欠だと考えています。ただし、副業はあくまで自己責任で行いましょう。
なぜ副業が会社にバレるのか?
「副業が会社に知られたらどうしよう」という不安は、会社員が副業を行う上で大きな壁になります。
でも、なぜ副業はバレるのでしょうか?
バレてしまった人は何が原因だったのでしょうか?
実は、その多くは、住民税と自己開示が原因です。
副業がバレる原因は意外と身近なところにあります。
まずは、会社に知られないために、知っておくべきリスクと仕組みを解説していきます。
住民税の金額からバレる理由とは?
副業がバレる主な原因は、住民税の金額に違和感が生じることです。
住民税とは、前年の所得に応じて計算される、都道府県民税と市町村民税のことです。
前年の所得には、本業の給与だけでなく、副業の収入もすべて合算されます。
ほとんどの会社員は、給与から天引きという方法で住民税を納付しています。
※この給与からの天引きにより納付する方法を「特別徴収」といいます。
同じ給料の同僚より住民税が高いと、経理担当者に副収入を疑われるきっかけになります。
そのため、副業収入分の住民税を適切に納付する対策が必要になります。
具体的には、給与天引きではなく、自分で納める「普通徴収」を選択することで回避できます。
※「普通徴収」の詳細や手続きについては後述します。
自分から話してしまう
意外に多いのが、自分から話してしまうケースです。
副業が順調に進んでいると、つい嬉しくなり、人に話したくなるものです。
飲み会の場など、気が緩んだ時に「実は副業で○○しててさ・・・」というように、同僚や友人などに話してしまう人も少なくありません。
ですが、その話がどこで誰に伝わるかはわかりません。
職場はうわさ話が広がりやすいものです。
あなたが信頼して話した相手だったとしても、意図せず上司の耳に入ってしまうことも十分考えられます。
また、SNSでの発信にも注意が必要です。
副業について発信しているアカウントを同僚に見つけられて発覚するケースもあります。
副業を会社に知られたくないなら、「誰にも言わない」「SNSに書かない」が鉄則です。
その他のきっかけ
住民税や口を滑らせる以外にも、こんなきっかけもあります。
・羽振りがよくなる
・勤務中に副業作業をしているのを目撃される
・副業先で働いている現場を偶然見られる
副業で収入が増えると、思わず贅沢したくなるものです。
それ自体はモチベーション維持にもつながることですし、決して悪いことではありません。
ですが、会社の同僚の目に留まるような目立つ行動をとってしまうと、「何でそんなに贅沢できるんだろう」と不審に思われるリスクがあります。
他にも、副業が忙しくなってくると、ついつい本業の合間にスマホで副業作業を行ってしまう人も少なくありません。
その様子を同僚に見られて、上司に報告されてしまう可能性もあります。
また、作業自体をしていなくても、休憩時間に作業しようと思って持ち込んだ副業関連の資料を見られてしまうといった発覚リスクもあります。
さらに、店舗でのアルバイトの現場を偶然見られてバレてしまう恐れもあります。
このように、会社にバレる原因は、些細なことや不注意から生まれることが多いです。
普段の行動や発言に気を配ることが大切です。
では、次に会社にバレずに副業をする具体的なポイントについて解説していきます。
バレずに副業するための3つのポイント
目立つ行動は避けて、誰にも言わない
これは心がけ次第で防げます。
決して誰にも話さないことはもちろん、急に高級車を買う、ブランド物で身を固めるといった目立つ行動は避けるように心がけるだけで、発覚リスクを最小限に抑えることが可能です。
とはいえ、人に話すことで、努力や成果を認めてもらいたくなる気持ちもよくわかります。
また、せっかく副収入を得たのだから、贅沢をしたくなることもあるでしょう。
そんな時は、家族や社外の仲間にだけ話し、贅沢も家族と楽しむなど、同僚の目につかない工夫が大切です。
アルバイト(特に勤務地に出向くもの)は避ける
会社に知られず副業をするなら、勤務地に出向く必要があるアルバイトは避けるのが賢明です。
理由は2つあります。
ひとつは、アルバイトの場合、受け取る報酬が給与所得になってしまうため、住民税の納付方法が、給与から天引きされる「特別徴収」になってしまうことです。
特別徴収は、主たる給与支払先(つまり本業の会社)からの天引きで処理される仕組みです。
つまり、アルバイトの副業で収入を増やせば増やすほど、本業の会社に通知される住民税の金額に違和感が生まれる原因となります。
※より具体的な住民税の内容に関しては、「税知識の基本」パートで解説しています。
もうひとつは、勤務地で働く必要があるアルバイトは、単純に目撃リスクがあるからです。
普段の生活圏でアルバイトをしてしまうと、同僚や知人に見られてしまう可能性は避けられません。
どうしてもアルバイトを選択したい場合は、パソコンやスマホだけで完結する在宅ワークなどのジャンルを選択しましょう。
最後に、これは会社バレとは別の視点ですが、アルバイトのような労働時間=収入の働き方は、自分が働けなくなった瞬間、収入が途絶えてしまうリスクがあります。
副業をするなら、時間に縛られずに収入が生まれる「資産型副業」を選ぶ視点も大切です。
本業と副業はしっかりと分ける
会社にバレないという視点に限らず、副業に取り組む基本的な考え方として、本業と副業の線引きをしっかりとすることはとても大切です。
これは、安心して副業に取り組むためにも重要なポイントになります。
就業時間中は副業の作業や連絡を避け、本業のパフォーマンスを維持しましょう。
また、昼休みや通勤時間であっても、会社のパソコンや社用スマホを利用することは避け、会社のシステムに履歴が残らないように注意しましょう。
仮に本業に支障が出たり、副業を疑われると、継続が難しくなる可能性があります。
さらに、副業の業種選びにも配慮が必要です。
本業と同業種や、関連業種を選択してしまうと、万が一副業を会社に知られてしまった場合に、利益相反を疑われかねません。
副業に臨む姿勢としては、本業と同じ熱量で取り組むことが理想ですが、線引きを意識して本業の責任を果たしつつ、時間やエネルギーの配分を計画的に行うことが大切だと思います。
知らないと損する税知識の基本
ここまで、会社に副業がバレる理由とその回避方法について解説してきました。
ここからは、副業に関する基本的な税知識と、バレる大きな要因となる住民税の仕組みについて詳しく説明していきます。
副業に関する税金の種類と基本知識
副業をする上で、必ず押さえておきたいのが「税金の基本」です。
税金に無頓着なまま副業を続けてしまうと、後から思わぬトラブルに発展することもあります。
ここでは、会社員が副業をする際に最低限知っておきたい「収入の種類と税金の種類」、「どのように課税されるか」という基本をおさえておきましょう。
収入の種類
副業で得た収入は、その種類によって課税区分が異なります。
代表的なものは次の2つです。
①給与所得
主に、アルバイトやパートなど、雇用契約を結んで給与としてお金をもらう場合は「給与所得」として扱われます。
支払方法が振り込み、現金手渡しということは関係ありません。
給与所得の場合、給与明細に「源泉徴収税」が記載されるのが一般的で、勤務先(副業先)があらかじめ税金を差し引いて給与を支払ってくれます。
ただし、年末調整に関しては本業の勤務先のみでしか行われないため、副業の所得については自分で確定申告をする必要があります。
給与所得は、住民税の納付方法の視点から、会社にバレたくない人にとって注意すべき種類の所得です。
※お住いの自治体によっては副業分の給与所得を普通徴収に変更できる場合もありますが、事業所得に比べて柔軟ではない傾向があります。
②雑所得、事業所得
一方、在宅ワークやフリーランス、ブログ収益、投資収益など、雇用契約のない収入は「雑所得」または「事業所得」として扱われ、確定申告を行うことで納税します。
事業所得の場合、確定申告の際に、住民税の納付方法を普通徴収(自分で納付する方法)とすることができるため、発覚のリスクを減らせる種類の所得といえます。
ですが、お住いの自治体の対応や副業収入の状況によって、特別徴収を完全に回避できない場合もあるので注意が必要です。
なお、副業収入が事業所得にあたるかどうかは、売上や活動の規模、継続性などを基準として税務署が判断します。
少し話は飛躍しますが、ここで、一つ注意してほしいことをお伝えします。
クラウドソーシングサービスなどを活用した、在宅ワークの業務委託の場合、一般的には、雑所得・事業所得となりますが、最終的な判断は税務署に委ねられます。
雇用契約に近い勤務実態の場合は、給与所得に分類される可能性もあります。
税金の種類
①所得税
所得税とは1年間の所得(=収入から必要経費を差し引いた金額)に対してかかる国税です。
会社員の場合、会社が給与から源泉徴収を行い、納税者の代わりに所得税を納付しています。
一方、給与所得者が得た副業所得に関しては、年間で20万円を超える場合には自分で確定申告を行い、所得税を納付する必要があります。
この年間20万円未満の場合は確定申告が不要という仕組みは、給与所得者向けの特例です。
副業所得が年間20万円を超える場合には、確定申告を行い所得税を自分で納める必要があることを覚えておきましょう。
※確定申告の方法については、この後詳しく解説します。
②住民税
住民税とは、前年の所得に応じて課税される地方税です。
会社員の場合、一般的に特別徴収(給料天引き)によって納付しています。
副業の所得も住民税の課税対象となります。
所得が20万円を超える場合には、確定申告を行う際に、徴収方法を選択し、申告手続きを行います。
なお、所得税とは異なり、副業所得が20万円未満であっても、住民税の納付義務は生じます。
この場合は、自治体の役場や税事務所で申告手続きが必要です。
③その他の税
このほかにも、個人事業税や消費税といった税金があります。
副業初期の段階では無関係なことが多いですが、将来的に大きくビジネスを展開したい場合は、個人事業税や消費税についても知っておくといいでしょう。
確定申告の方法
副業で得た収入が一定額を超えた場合は、確定申告が必要です。
ここでは、基本的な手順と注意点を簡単にまとて説明します。
確定申告の時期
確定申告の受付期間は、原則として毎年2月16日から3月15日です。
この期間内に、前年1月1日から12月31日までの所得について申告を行います。
申告の方法
①税務署の窓口で申告する
お住いの地域の管轄税務署窓口に必要書類を提出する、最もオーソドックスな方法です。
確定申告期間は、無料の税務相談を受けている自治体もあり、初めての方や申告内容に不安のある方にお勧めです。
僕も初めはよくわからず、税務署で書類の書き方などを確認しながら確定申告書を作成していました。
ただし、確定申告の時期の税務署は非常に混み合います。
相談や申告の際は、時間に余裕をもって窓口へ行くようにしましょう。
②郵送で申告する
必要書類に記入・準備して、税務署へ郵送して申告する方法です。
書類の記入に慣れた方にとっては、混み合う窓口へ行く必要がないため便利です。
ですが、提出した書類に不備があると、修正の手続きに時間がかかる場合もあります。
申告期限内に手続きを完了できるように、時間に余裕を持って投函しましょう。
③e-Tax(インターネット申告)を利用して申告する
近年主流になりつつあるのが、e-Taxです。
インターネット経由のため、自宅で好きな時間に申告を行うことができます。
マイナンバーカードとスマホもしくはカードリーダーがあれば、利用が可能です。
必要な書類
確定申告の際は、以下のような書類が必要です。
- 本業の源泉徴収票
- 副業の収入を証明する書類(支払調書、振込明細、売上記録など)
- 副業にかかった経費の領収書やレシート
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
- 身分証明書、印鑑
- 振込先の銀行口座情報
副業で経費を計上する場合は、領収書やレシートをしっかり保管しておきましょう。
申告のポイント
最後に、確定申告で失敗しないためのポイントをお伝えします。
- 副業の収入・経費は日頃から記録しておく
- 必要書類を早めに準備する
- 申告期限を過ぎないよう注意する
- 住民税の徴収方法(普通徴収か特別徴収か)を申告書で選択する
特に「住民税の徴収方法」は、会社にバレないようにするための重要なポイントです。
申告書の該当欄で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶようにしましょう。
会社員が始めやすい副業ジャンルとは?
ここまで、副業に関する税金や注意点について解説してきましたが、事業所得となる副業はどのようなジャンルなのか気になる方も多いでしょう。
会社員がバレずに副業を行うために重要なことは、「時間と場所を選ばずに働ける、匿名性の高いジャンルを選ぶこと」です。
ここでは、会社員でも始めやすい副業のジャンルについて簡単にご紹介します。
① スキルを活かした在宅ワーク
自分の知識やスキルを活かせる、在宅型の仕事です。
例えば、ライティング・動画編集・プログラミング・デザインなど、クラウドソーシングサイトを利用して案件を受注できます。
- パソコンとネット環境があれば始められる
- 収入の上限が比較的高く、将来的に独立も視野に入れられる
- 雇用契約ではないので、事業所得扱いにしやすい
② ネットショップ・転売
ECサイトやフリマアプリを活用して、物販で収益を上げる方法です。
在庫管理や仕入れが必要ですが、仕組みがわかれば継続的な利益を目指せます。
- 不用品販売から始められる
- 小規模なら少額の資金でスタート可能
- 継続的に売上が出る仕組みづくりがポイント
③ ブログ・アフィリエイト
自分のメディアを作り、広告収入や成果報酬を得る方法です。
短期的に稼ぐのは難しいですが、積み上げ型で長期的な副収入源になるのが魅力です。
- 初期費用が少なく、在宅で始められる
- 会社にバレにくく、事業所得扱いにもしやすい
- 成果が出るまで時間がかかる
④ コンテンツや電子書籍販売
自分の知識やノウハウなどを、コンテンツや電子書籍として販売し収益を得る方法です。
専門知識が必要で、制作に時間はかかりますが、一度作り上げたコンテンツは資産となります。
- 初期費用をかけずに、在宅でもできる
- 専門知識が必要になる
- 匿名性が高く、資産性のある副収入源になる
ここで紹介したのはほんの一部のジャンルです。
このように、アルバイトではない匿名性の高いジャンルも存在します。
あなたの状況や理想の働き方に合ったジャンルを選び、自分に合った副業にチャレンジしてみてください。
※もっと詳しく副業ジャンルについて解説した記事もあります。
【自分に合った副業ジャンル】を探したい方はこちらも参考にしてください。
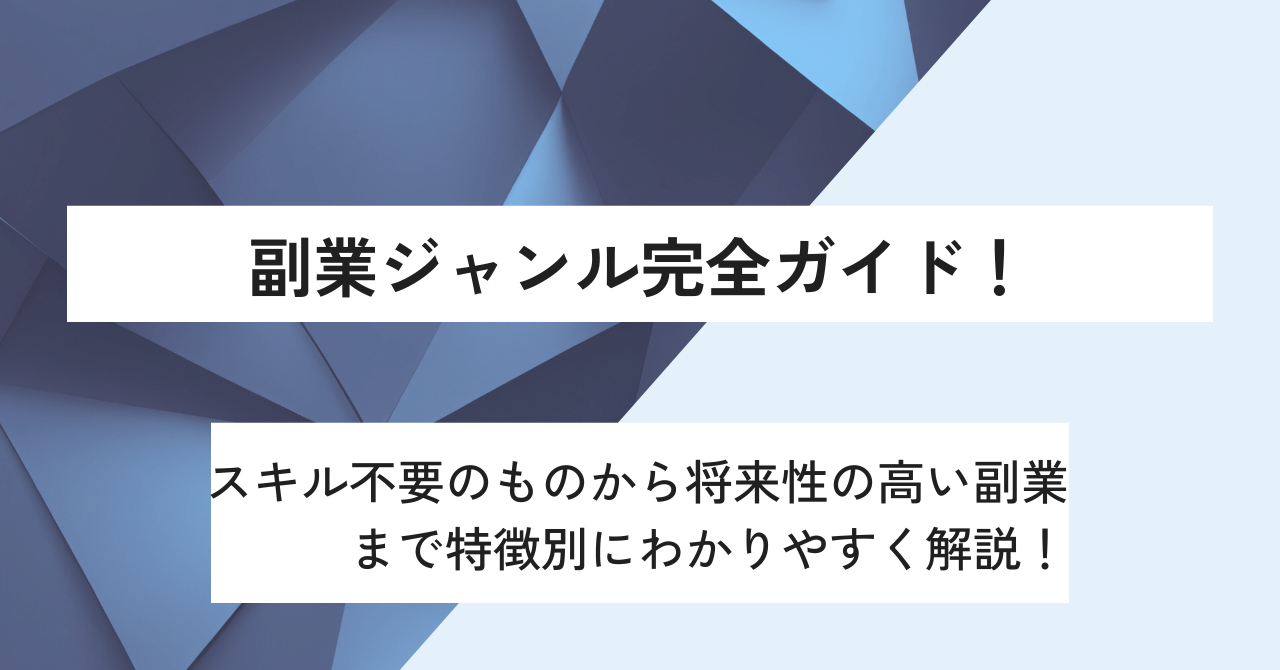
まとめ
この記事では、副業が会社にバレる理由と回避するためのポイント、税金の知識、会社員におすすめの副業ジャンルについて解説してきました。
最後に、僕からあなたへのメッセージをお伝えします。
会社が禁止しているから副業できないというのは、一般的には正しい考え方かもしれません。
ですが、生活の保障すべてを会社だけに委ねることは、今の時代むしろリスクといえます。
たしかに、会社は今のあなたの生活を保障してくれています。
しかし、それが未来永劫続くわけではありません。
副業収入を得て、自分と家族の生活は自分が守るという考え方も、これからの時代には必要だと思います。
本業と副業を区別する、利益相反しない業務を選択する、ということを守った副業であれば、民法・労働基準法の観点からは、原則自由です。
もちろん、すべて自己責任ではありますが、一歩を踏み出してみる価値はあると思います。
以下の記事で副業成功のマインドから具体的ステップまで詳しく解説しています。将来の選択肢を広げたい方は是非チェックしてみてください。

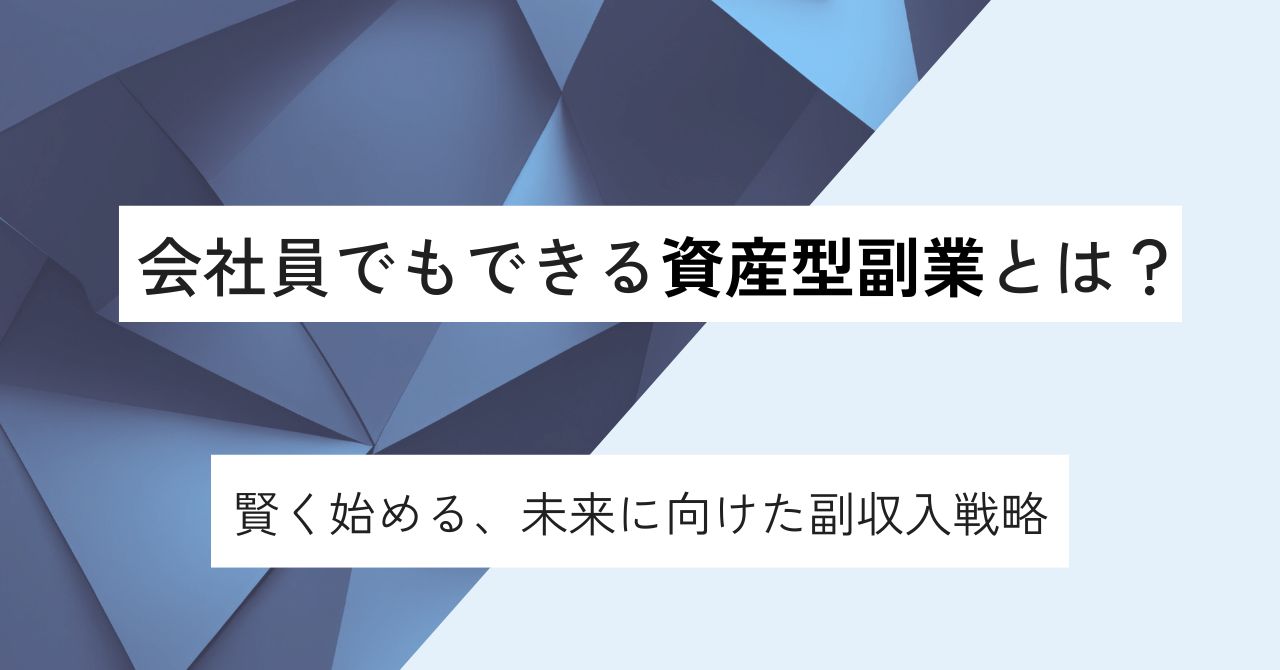
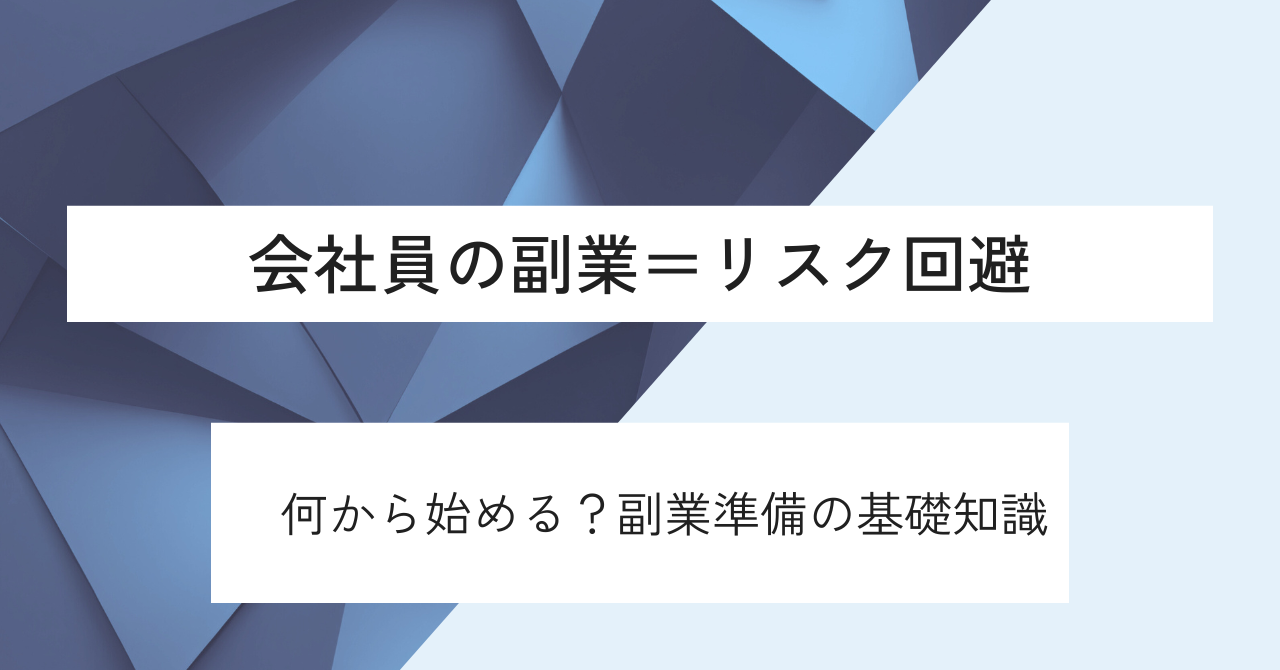
コメント